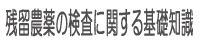全世界で行われている残留農薬検査

全世界で行われている残留農薬検査
日本の中で生産されている農作物の残留農薬検査は地方自治体で行われていますが、輸入品においては空港や港の検疫所で分析を行い合格品だけを受け入れているなどの仕組みがあります。
いずれも不合格になると、流通できなくなるので処分や返品などの事態になり生産者や輸出側は大きなダメージになるなど全世界、世界レベルで行われていることが分かるのではないでしょうか。
使用を認める物質のリストでもあるポジティブリストと呼ぶものを作り、使用を認める物質以外は原則として使用を禁止する規制の仕組みをポジティブリスト制度と呼びます。
このポジティブリスト制度を理解することで安心して農作物を食べることに繋がりますが、消費者側からすると農薬が残っても良い量もしくは割合と聞いても不安になるだけです。
残留農薬基準は、生涯にわたり毎日摂取し続けたとしても健康に害を与えない量、このような設定が行われているものです。
それと、残留農薬はゼロになるものはなく不検出の表現で伝えられるのが特徴です。
残留農薬検査で地域の食の安全を守る施設がオススメ
残留農薬検査を行っている施設では、作物ごとに決められた使用農薬と残留基準値が守られていることを確認し農産物を主な原料にした加工食品やその原料についても調査分析します。
残留農薬の調査分析施設では、まず検体を細かく粉砕し決められた量を測定して均一化し試薬を使用して農薬を抽出し抽出した液から葉緑素や油分を除去していきます。
次に試験液を分析機器で測定し、測定された結果を解析し農薬の種類と濃度を判定していきますが残留農薬検査では農薬の特性に合わせて、2種類の機器を使用して分析しております。
質量分析計は、農薬の分子量や構造情報が得ることが可能なため定性能力に優れているだけではなく非常に感度が高くで0.01PPMと言う微量でも検出することができるのです。
施設では一人一人が食の安全確保に取り組み、それがつながる食の安全をイメージしたサークルをコンセプトとしていて地域の安全情報を科学的な視点からお伝えしています。